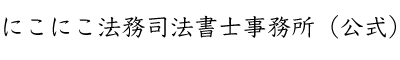公正証書遺言
- 作成者・関与者: 公証人が作成し、証人2名以上が必要です。
- 費用: 公証人への手数料がかかります(財産額によって変動、数万円〜)。その他、必要書類の取得費用、証人への謝礼、専門家への依頼費用などがかかる場合があります。
- 作成の手間: 公証役場に出向く必要があります(病気等で出向けない場合は公証人の出張も可能)。公証人との打ち合わせが必要です。
- 形式の有効性: 公証人が法律の専門家として関与するため、形式の不備で無効になる心配がほとんどありません。内容についても法的に整理されたものになります。
- 保管: 原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失、隠匿、改ざんのリスクがありません。
- 検認: 家庭裁判所での「検認手続き」が不要なため、相続開始後の手続きがスムーズです。
- 内容の秘密性: 公証人や証人に内容が知られます。
自筆証書遺言
- 作成者・関与者: 遺言者本人が全文を自筆で作成します(財産目録はパソコン等でも可)。証人は不要です。
- 費用: 基本的に作成費用はかかりません。法務局の保管制度を利用する場合は手数料がかかります(数千円程度)。
- 作成の手間: 自分一人で手軽に作成できます。
- 形式の有効性: 厳格な要件(全文自筆、日付、氏名、押印など)を満たさないと無効になるリスクがあります。訂正方法も厳格に定められています。
- 保管:
- 自宅等で保管する場合: 紛失、盗難、改ざん、相続人による隠匿のリスクがあります。
- 法務局の保管制度を利用する場合: 法務局で原本と画像データが保管されるため、紛失、隠匿、改ざんのリリスクが低いです。
- 検認:
- 自宅等で保管する場合: 相続発生後に家庭裁判所での「検認手続き」が必要となり、時間と手間がかかります。
- 法務局の保管制度を利用する場合: 検認手続きが不要です。
- 内容の秘密性: 遺言者本人以外に内容を知られることがありません。
まとめると、公正証書遺言は費用や手間はかかるものの、法的な確実性や保管の安全性が高く、相続発生後の手続きがスムーズに進む点が大きなメリットです。一方、自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、形式不備による無効のリスクや紛失・改ざんのリスクがありましたが、近年導入された法務局の保管制度を利用することで、これらのデメリットの一部を解消できるようになっています。